採用と人的資本の最前線
マスメディアン編集部 2024.09.18
- 人的資本
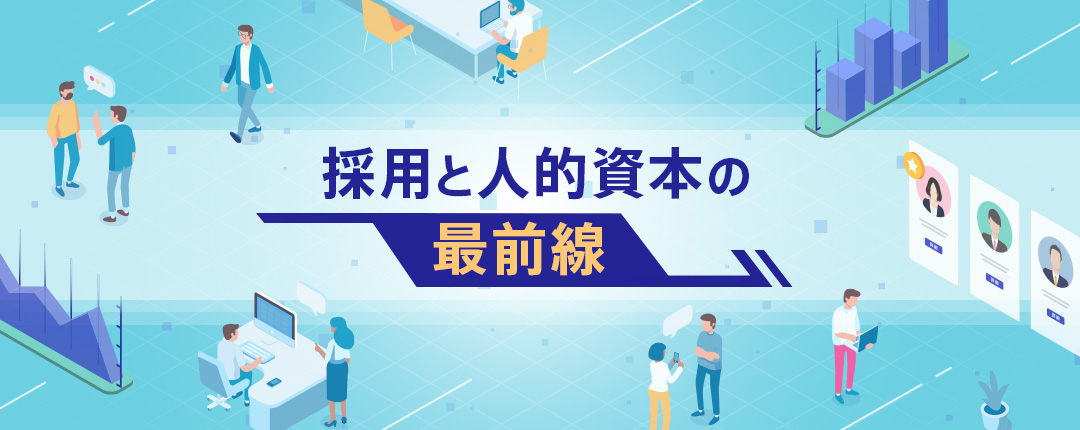
人的資本は、今日の企業経営においてこれまで以上に重要な要素となっています。市場の変化や労働人口の不足に対応し、持続的な企業成長を達成するためには、採用や組織づくりの現場に人的資本の考え方を取り入れる必要があるでしょう。
慶應義塾大学大学院 特任教授の岩本隆先生による、採用と人的資本の最新情報についてのコラムをお届けします。
■「ISO 30414:2025」における要求人的資本メトリック(2025.12.01公開)
2025年にアップデートされたISO 30414:2025では、企業規模を問わずすべての企業に開示が要求される、7つの人的資本領域における14のメトリックが示されました。この要求人的資本メトリック(Required Metrics)について、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■人的資本報告・開示の国際規格「ISO 30414」 2025年アップデートのポイント(2025.11.17公開)
2025年8月、人的資本の報告・開示に関する国際規格「ISO 30414」の第2版が発行されました。タイトルが「ガイドライン」から「要求・推奨」に変更されたほか、メトリックが整理されるなどさまざまな変更が行われています。慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■HRテクノロジー大賞(2025.11.03公開)
2016年に始まり2025年で10回目を迎えたHRテクノロジー大賞は、人事や人材マネジメント分野でのテクノロジー活用の先進事例を表彰するものです。生成AIやAIエージェントの活用が進むHRテクノロジーの進化にも注目が集まる同賞の10年間について、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■第3回 オープンバッジ大賞(2025.10.13公開)
オープンバッジとは、デジタル証明書としてスキルや資格を可視化する仕組みの一つです。近年では、中途採用の場で求人企業と求職者のスキルマッチングを促進するツールとして注目されています。その活用方法や可能性について、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■100億企業創出の加速に向けた政策(2025.09.29公開)
中小企業庁は2025年、売上高100億円を目指す挑戦的な企業を支援し、新たな成長モデルを提示する「100億宣言」プロジェクトを始動しました。売上高の成長を実現するために経営者や人事・採用担当者が果たすべき役割について、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■経済産業政策新機軸によって実現を目指す2040年の就業構造(2025.09.12公開)
2040年を見据えた労働市場の変化が注目されています。生成AIやロボットの普及により、事務や販売職で労働力の余剰が生じる一方、研究者や技術者の不足が予測されるなど、職種ごとの「需給ギャップ」が顕著になる可能性があります。このギャップに対応するための政策や取り組みを、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■タレントアクイジション領域のHCMアプリケーション世界市場の最新動向(2025.09.01公開)
人的資本管理のためのアプリケーションの世界市場規模が急拡大しています。その3大セグメントのうちの1つ、タレントアクイジション(人材獲得)領域の市場について、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■HCMアプリケーションの世界市場の最新動向(2025.08.18公開)
人事業務の効率化や採用最適化を支援するHCMアプリケーションの市場が世界で急成長しています。2024年の市場規模や成長予測について、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■スキルベース人材育成に向けた政策(2025.08.04公開)
2025年5月、経済産業省は「スキルベースの人材育成」に向けた報告書を公表しました。経済発展と社会的課題の解決を両立する「Society 5.0」の実現には日本企業全体のDXが不可欠ですが、そのための人材育成には「学ぶ人々の現状が可視化されていない」という課題があるといいます。これから加速するスキルベース人材育成のための仕組みについて、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■産業人材育成プラン(2025.07.16公開)
DX、情報通信などを支える人材をどう育てればよいのでしょうか。政府が2025年6月に発表した「産業人材育成プラン」では、産業構造の変化に応じた人材の確保と育成が重点施策に位置付けられました。学校教育からリスキリング、産学官の連携まで、企業の採用・育成にも関わる支援策の全体像を、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■三位一体の労働市場改革(2025.07.02公開)
2025年6月に発表された骨太方針では、「三位一体の労働市場改革」がアップデートされました。政府はリスキリング、ジョブ型雇用、成長産業への労働移動を一体で進める方針を明確化しています。企業の採用や人材育成にも影響する最新の政策動向を、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■雇用仲介事業者に関連するルールのアップデート(2025.06.18公開)
採用活動へのテクノロジー活用の広がりを背景に、職業紹介・募集情報サービスの法的ルールが見直されています。2025年4月の職業安定法改正により、求人情報の取り扱いや契約の明示などが変更され、企業にとっても正しい理解が求められるタイミングです。近年の雇用仲介事業者に関連する制度改正のポイントを、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■EOR(Employer of Record:エンプロイヤー・オブ・レコード)(2025.06.04公開)
現在、人事領域で世界的な注目を集める「EOR(エンプロイヤー・オブ・レコード)」は、「雇用代行」とも言われ、現地法人を持たずに海外人材を活用できる仕組みです。雇用手続きや給与支払いなどを代行するこのサービスは、労働人口減少に直面する日本企業でも活用が始まっています。急成長するEOR市場の動向と日本での広がりを、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■中堅企業の人材確保・育成政策(2025.05.21公開)
2024年に制度上「中堅企業」が定義され、成長支援に向けた政策が本格的に始まりました。経営人材や専門人材の確保、省力化投資や人的資本経営の地域展開など、幅広い施策が動き出しています。中堅企業の成長に向けた政策の全体像とポイントを、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■GEO(Generative Engine Optimization:生成エンジン最適化)(2025.05.07公開)
ChatGPTの登場以降、ユーザーの情報取得手段が検索エンジンから生成AIへと変化しつつあります。そこでSEOに代わり注目されているのが、生成AIに正しく参照されるための新たな対策「GEO(Generative Engine Optimization)」です。企業のマーケティング戦略にも影響を及ぼし始めるGEOについて、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■ナラティブマーケティング(2025.04.16公開)
企業が発信する一方的な「ストーリー」ではなく、顧客が共感し自ら語る「ナラティブ」が、医療やビジネスなどさまざまな領域で重要視されています。マーケティング領域において「ナラティブ」の持つ人の行動を変える力と、その活用の広がりについて、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■デジタルガバナンス・コード3.0(2025.04.02公開)
DXが企業経営に不可欠となる中、マーケティング領域でも戦略的なデジタル活用が求められています。マーケティングDXの成功に向けて導入すべき「デジタルガバナンス・コード3.0」は戦略策定をはじめ、組織づくりや人材育成においても指標とすることが可能です。慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■AIエージェント(2025.03.19公開)
「AIエージェント元年」と呼ばれる2025年、人材領域でも、自律的に判断・行動し、与えられた目標を達成する「AIエージェント」への関心が高まっています。ここ日本でも開発競争が激化するAIエージェントの最新動向について、慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■人材採用力向上に重要なウェルビーイング経営(2025.03.05公開)
「働き方改革」から「働きがい改革」へ。今、企業に求められるのは、単なる労働環境の整備ではなく、従業員のキャリアや働きがいを支える仕組みづくりです。ウェルビーイング経営の最新動向を、慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■スキル標準の広がり(2025.02.09公開)
「人材流動化時代」において、企業を超えて通用するスキル標準の活用が求められています。デジタルやグリーン分野をはじめ、宇宙や半導体領域にも広がるこの取り組みは、企業の人材育成や採用戦略にも新たな可能性をもたらします。慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■多様な人材の採用・活躍に求められるビロンギングの高い企業文化(2025.02.05公開)
近年、ダイバーシティ推進に加え、「ビロンギング(帰属意識)」を高める取り組み、つまり、異質な人材集団の中でも安心して活躍できる環境づくりが注目されています。ビロンギングが人材採用・定着に与える影響と、企業文化の新たな方向性について、慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授が、事例を交えながら解説します。
《詳細はこちら》
慶應義塾大学大学院 特任教授の岩本隆先生による、採用と人的資本の最新情報についてのコラムをお届けします。
■「ISO 30414:2025」における要求人的資本メトリック(2025.12.01公開)
2025年にアップデートされたISO 30414:2025では、企業規模を問わずすべての企業に開示が要求される、7つの人的資本領域における14のメトリックが示されました。この要求人的資本メトリック(Required Metrics)について、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■人的資本報告・開示の国際規格「ISO 30414」 2025年アップデートのポイント(2025.11.17公開)
2025年8月、人的資本の報告・開示に関する国際規格「ISO 30414」の第2版が発行されました。タイトルが「ガイドライン」から「要求・推奨」に変更されたほか、メトリックが整理されるなどさまざまな変更が行われています。慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■HRテクノロジー大賞(2025.11.03公開)
2016年に始まり2025年で10回目を迎えたHRテクノロジー大賞は、人事や人材マネジメント分野でのテクノロジー活用の先進事例を表彰するものです。生成AIやAIエージェントの活用が進むHRテクノロジーの進化にも注目が集まる同賞の10年間について、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■第3回 オープンバッジ大賞(2025.10.13公開)
オープンバッジとは、デジタル証明書としてスキルや資格を可視化する仕組みの一つです。近年では、中途採用の場で求人企業と求職者のスキルマッチングを促進するツールとして注目されています。その活用方法や可能性について、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■100億企業創出の加速に向けた政策(2025.09.29公開)
中小企業庁は2025年、売上高100億円を目指す挑戦的な企業を支援し、新たな成長モデルを提示する「100億宣言」プロジェクトを始動しました。売上高の成長を実現するために経営者や人事・採用担当者が果たすべき役割について、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■経済産業政策新機軸によって実現を目指す2040年の就業構造(2025.09.12公開)
2040年を見据えた労働市場の変化が注目されています。生成AIやロボットの普及により、事務や販売職で労働力の余剰が生じる一方、研究者や技術者の不足が予測されるなど、職種ごとの「需給ギャップ」が顕著になる可能性があります。このギャップに対応するための政策や取り組みを、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■タレントアクイジション領域のHCMアプリケーション世界市場の最新動向(2025.09.01公開)
人的資本管理のためのアプリケーションの世界市場規模が急拡大しています。その3大セグメントのうちの1つ、タレントアクイジション(人材獲得)領域の市場について、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■HCMアプリケーションの世界市場の最新動向(2025.08.18公開)
人事業務の効率化や採用最適化を支援するHCMアプリケーションの市場が世界で急成長しています。2024年の市場規模や成長予測について、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■スキルベース人材育成に向けた政策(2025.08.04公開)
2025年5月、経済産業省は「スキルベースの人材育成」に向けた報告書を公表しました。経済発展と社会的課題の解決を両立する「Society 5.0」の実現には日本企業全体のDXが不可欠ですが、そのための人材育成には「学ぶ人々の現状が可視化されていない」という課題があるといいます。これから加速するスキルベース人材育成のための仕組みについて、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■産業人材育成プラン(2025.07.16公開)
DX、情報通信などを支える人材をどう育てればよいのでしょうか。政府が2025年6月に発表した「産業人材育成プラン」では、産業構造の変化に応じた人材の確保と育成が重点施策に位置付けられました。学校教育からリスキリング、産学官の連携まで、企業の採用・育成にも関わる支援策の全体像を、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■三位一体の労働市場改革(2025.07.02公開)
2025年6月に発表された骨太方針では、「三位一体の労働市場改革」がアップデートされました。政府はリスキリング、ジョブ型雇用、成長産業への労働移動を一体で進める方針を明確化しています。企業の採用や人材育成にも影響する最新の政策動向を、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■雇用仲介事業者に関連するルールのアップデート(2025.06.18公開)
採用活動へのテクノロジー活用の広がりを背景に、職業紹介・募集情報サービスの法的ルールが見直されています。2025年4月の職業安定法改正により、求人情報の取り扱いや契約の明示などが変更され、企業にとっても正しい理解が求められるタイミングです。近年の雇用仲介事業者に関連する制度改正のポイントを、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■EOR(Employer of Record:エンプロイヤー・オブ・レコード)(2025.06.04公開)
現在、人事領域で世界的な注目を集める「EOR(エンプロイヤー・オブ・レコード)」は、「雇用代行」とも言われ、現地法人を持たずに海外人材を活用できる仕組みです。雇用手続きや給与支払いなどを代行するこのサービスは、労働人口減少に直面する日本企業でも活用が始まっています。急成長するEOR市場の動向と日本での広がりを、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■中堅企業の人材確保・育成政策(2025.05.21公開)
2024年に制度上「中堅企業」が定義され、成長支援に向けた政策が本格的に始まりました。経営人材や専門人材の確保、省力化投資や人的資本経営の地域展開など、幅広い施策が動き出しています。中堅企業の成長に向けた政策の全体像とポイントを、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■GEO(Generative Engine Optimization:生成エンジン最適化)(2025.05.07公開)
ChatGPTの登場以降、ユーザーの情報取得手段が検索エンジンから生成AIへと変化しつつあります。そこでSEOに代わり注目されているのが、生成AIに正しく参照されるための新たな対策「GEO(Generative Engine Optimization)」です。企業のマーケティング戦略にも影響を及ぼし始めるGEOについて、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■ナラティブマーケティング(2025.04.16公開)
企業が発信する一方的な「ストーリー」ではなく、顧客が共感し自ら語る「ナラティブ」が、医療やビジネスなどさまざまな領域で重要視されています。マーケティング領域において「ナラティブ」の持つ人の行動を変える力と、その活用の広がりについて、慶應義塾大学大学院 講師の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■デジタルガバナンス・コード3.0(2025.04.02公開)
DXが企業経営に不可欠となる中、マーケティング領域でも戦略的なデジタル活用が求められています。マーケティングDXの成功に向けて導入すべき「デジタルガバナンス・コード3.0」は戦略策定をはじめ、組織づくりや人材育成においても指標とすることが可能です。慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■AIエージェント(2025.03.19公開)
「AIエージェント元年」と呼ばれる2025年、人材領域でも、自律的に判断・行動し、与えられた目標を達成する「AIエージェント」への関心が高まっています。ここ日本でも開発競争が激化するAIエージェントの最新動向について、慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■人材採用力向上に重要なウェルビーイング経営(2025.03.05公開)
「働き方改革」から「働きがい改革」へ。今、企業に求められるのは、単なる労働環境の整備ではなく、従業員のキャリアや働きがいを支える仕組みづくりです。ウェルビーイング経営の最新動向を、慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■スキル標準の広がり(2025.02.09公開)
「人材流動化時代」において、企業を超えて通用するスキル標準の活用が求められています。デジタルやグリーン分野をはじめ、宇宙や半導体領域にも広がるこの取り組みは、企業の人材育成や採用戦略にも新たな可能性をもたらします。慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■多様な人材の採用・活躍に求められるビロンギングの高い企業文化(2025.02.05公開)
近年、ダイバーシティ推進に加え、「ビロンギング(帰属意識)」を高める取り組み、つまり、異質な人材集団の中でも安心して活躍できる環境づくりが注目されています。ビロンギングが人材採用・定着に与える影響と、企業文化の新たな方向性について、慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授が、事例を交えながら解説します。
《詳細はこちら》
■地域の人事部(2025.01.15公開)
2025年は、中堅企業に向けた人的資本経営の政策が本格始動を迎えます。特に取り組みの1つである「地域の人事部」は、地域の企業群が自治体などと連携して経営人材の確保やキャリアステップの構築を行うことで、中堅企業の人材確保から育成や定着まで大きな役割を果たすことが期待されています。今後の政策の動きや、地域の人事部の取り組みなどを、慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■候補者体験(Candidate Experience)(2024.12.18公開)
人材採用において「候補者体験(Candidate Experience)」を重要視する動きが、ここ日本でも広がりつつあります。労働人口の不足が深刻化する中、人材採用においてますます重要になる候補者体験と、それを向上させるための採用活動について、慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■女性活躍推進法改正の方針(2024.12.04公開)
2025年に向けて、女性活躍推進法の改正案の検討が進められています。改正案では、「女性の管理職比率」や「男女別の登用比率」などの開示の必須化、対象範囲を101人以上の企業まで拡大することなどが見込まれています。女性活躍推進の取り組みの状況や、注目すべきポイントについて、慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■エンプロイヤーブランド(2024.11.20公開)
労働人口不足が深刻化する中で、自社の人材採用力を客観的に理解することはますます重要になります。他社に比べた強み弱みを明確にし、エンプロイヤーブランディングの施策を行うために、自社の「エンプロイヤーブランド」を測定する11の方法を、慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■マイクロクレデンシャル(2024.11.06公開)
従来の学歴基準では難しい、仔細なスキルや知識の認証基準である「マイクロクレデンシャル」。世界でも日本でも広がってきている、「オープンバッジ」を活用したスキルベースの組織マネジメントへの応用が可能なことから、注目が集まりつつあります。マイクロクレデンシャルの定義と活用事例について、慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■人的資本経営に関連する国際標準(2024.10.16公開)
人的資本経営を語る際によく取り上げられるテーマである、「イノベーティブな組織づくり」や「パーパス経営」。実はこれらは、ISO(国際標準化機構)で国際規格が開発されています。人材マネジメントに関連する国際規格について、慶應義塾大学大学院 特任教授の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■ジョブ型人事のためのスキルプラットフォーム(2024.10.02公開)
2024年8月、「ジョブ型人事指針」が公表されました。日本企業が競争力を維持するためにジョブ型人事の導入を促すことが目的で、その意義や導入事例が紹介されています。ジョブ型人事の基礎となる「ジョブ」や「スキル」の整理、またスキルマップの活用方法について、慶應義塾大学大学院 特任教授の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■CMOからCGOへ(2024.09.18公開)
2024年に米国企業で最も速く増えるといわれている役職「CGO(最高事業成長責任者)」。CMOに代わって設置されることもあり、企業全体の成長を統括するポジションです。マーケティングにとどまらず、市場を創出し、事業を成長させる役割を担います。日本企業でも少しずつ導入が進むCGOとは。
《詳細はこちら》
■中堅企業元年(2024.08.21公開)
2024年は「中堅企業」を重点的に支援するための改正法が成立した「中堅企業元年」。そのうち、賃上げや国内での設備投資に積極的な企業は「特定中堅企業」と位置付け、法人税などが優遇されます。そうした中堅企業が今後、人的資本を強化するに当たっては、マーケティングや研究開発の人材が重要となります。
《詳細はこちら》
■C-Suite 3.0(2024.08.07公開)
C-Suite(Cスイート)とは、CXOと呼ばれるコーポレート・エグゼクティブを指します。1920年代に導入が始まり、1世紀を経た現在では、CXO間の連携が重視される「C-Suite 3.0時代」に突入しました。この時代においては、次世代の経営人材である「π型人材」の重要性がますます高まっています。CXOの役割と「π型人材」の必要性について解説します。
《詳細はこちら》
■パブリックアフェアーズ(2024.07.17公開)
マーケティングの重要な役割の1つに「市場創造」があります。特にカーボンニュートラルなどの社会課題を解決するための市場を創造するには、世の中との関係を築く「PR」と、政策関係者との関係を築く「GR」の両方が必要です。これらを統合した「パブリックアフェアーズ」という考え方が注目されています。日本におけるパブリックアフェアーズの考え方とその重要性を解説します。
《詳細はこちら》
■経営におけるPRの重要性の高まり(2024.07.03公開)
現代のビジネスにおいて、PRは経営に欠かせない要素となっています。日本では「PR」は「宣伝」として理解されがちですが、本来はもっと広い意味を持ち、経営戦略の一環として重要視されています。米国ではMBAプログラムにもPRが含まれており、その重要性が強調されています。経営におけるPRの役割とその重要性を解説します。
《詳細はこちら》
■採用ブランドを高めるための人的資本開示(2024.06.19公開)
人的資本開示が国内外で進んでいます。日本では資本市場だけでなく、労働市場に向けた情報開示の重要性が高まっています。採用ブランドの構築には、適切な人的資本開示が不可欠であり、全ての従業員が自社の人的資本経営についての物語(ナラティブ)を共有することが求められます。
《詳細はこちら》
■フリーランス新法(2024.06.05公開)
通称「フリーランス新法」が2024年11月に施行されます。この法律は、フリーランスとの取引適正化と就業環境整備を目指し、フリーランスと取引する事業者に対して、給付内容の明示、ハラスメント対策、中途解除の事前予告などを求めています。法律の制定経緯とその内容を詳しく解説します。
《詳細はこちら》
■キャリアマップ(2024.05.15公開)
ギャラップ社が定義した「ウェルビーイングの5つの構成要素」のうち、最も大きく寄与するのが「キャリアウェルビーイング」であるという研究結果があります。キャリアウェルビーイングを高めるためには、「キャリアマップ」の活用が不可欠です。
《詳細はこちら》
■労働人口問題(2024.05.01公開)
2024年現在、日本における労働人口不足は、あらゆる企業にとって深刻な経営課題です。10~20年後には、人工知能やロボットで労働人口を補うというシナリオも考えられていますが、その他にどのような施策があり得るのでしょうか。労働人口問題の概況と今後の展望を解説します。
《詳細はこちら》
■スキル標準の活用に向けて(2024.03.20公開)
スキルベース採用の実現に向けて、「スキル標準」の活用が欧米を中心に進んでいます。スキル標準とは、企業や業界を超えて共通で利用できるスキルマップのことを指します。日本でもスキル標準は策定されていますが、その活用はまだ初期段階です。今後の活用推進の取り組みと見通しを解説します。
《詳細はこちら》
■スキルのデジタル証明(2024.03.06公開)
「スキルベース採用」が活発化する中で、個人が持つスキルを証明する手段として「オープンバッジ」の利用が進んでいます。オープンバッジとは何か、また採用に活用する際に採用担当者が知っておくべきポイントについて解説します。
《詳細はこちら》
■採用アナリティクスツール(2024.02.21公開)
「採用活動のボトルネックとなっている工程を特定したい」「採用経路別のコストや成果を明確にしたい」などのニーズに応えるため、人材採用の成果を高める採用アナリティクスツールが注目されています。近年、これらのツールの市場は急速に拡大しており、その現状と全体像を解説します。
《詳細はこちら》
■人材採用の基本メトリック(2024.02.07公開)
ISOは、人材採用を定量的に評価するための基本メトリックを示しています。「惹きつける/発掘する/査定する/雇用する」という人材採用の4側面をどのように測定するべきか、その指標について解説します。
《詳細はこちら》
■人材採用の国際標準化(2024.01.17公開)
人的資本報告のガイドライン(ISO 30414)をはじめ、人材分野における国際規格の開発が進んでいます。これらの国際標準は、人材採用の戦略策定に役立てられており、「Attract(惹きつける)」「Source(発掘する)」など、採用の各側面のROIを定量化して人材採用力を高めるために活用されています。人材採用の国際標準化の全体像を解説します。
《詳細はこちら》
2025年は、中堅企業に向けた人的資本経営の政策が本格始動を迎えます。特に取り組みの1つである「地域の人事部」は、地域の企業群が自治体などと連携して経営人材の確保やキャリアステップの構築を行うことで、中堅企業の人材確保から育成や定着まで大きな役割を果たすことが期待されています。今後の政策の動きや、地域の人事部の取り組みなどを、慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■候補者体験(Candidate Experience)(2024.12.18公開)
人材採用において「候補者体験(Candidate Experience)」を重要視する動きが、ここ日本でも広がりつつあります。労働人口の不足が深刻化する中、人材採用においてますます重要になる候補者体験と、それを向上させるための採用活動について、慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■女性活躍推進法改正の方針(2024.12.04公開)
2025年に向けて、女性活躍推進法の改正案の検討が進められています。改正案では、「女性の管理職比率」や「男女別の登用比率」などの開示の必須化、対象範囲を101人以上の企業まで拡大することなどが見込まれています。女性活躍推進の取り組みの状況や、注目すべきポイントについて、慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■エンプロイヤーブランド(2024.11.20公開)
労働人口不足が深刻化する中で、自社の人材採用力を客観的に理解することはますます重要になります。他社に比べた強み弱みを明確にし、エンプロイヤーブランディングの施策を行うために、自社の「エンプロイヤーブランド」を測定する11の方法を、慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■マイクロクレデンシャル(2024.11.06公開)
従来の学歴基準では難しい、仔細なスキルや知識の認証基準である「マイクロクレデンシャル」。世界でも日本でも広がってきている、「オープンバッジ」を活用したスキルベースの組織マネジメントへの応用が可能なことから、注目が集まりつつあります。マイクロクレデンシャルの定義と活用事例について、慶應義塾大学大学院の岩本隆特任教授に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■人的資本経営に関連する国際標準(2024.10.16公開)
人的資本経営を語る際によく取り上げられるテーマである、「イノベーティブな組織づくり」や「パーパス経営」。実はこれらは、ISO(国際標準化機構)で国際規格が開発されています。人材マネジメントに関連する国際規格について、慶應義塾大学大学院 特任教授の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■ジョブ型人事のためのスキルプラットフォーム(2024.10.02公開)
2024年8月、「ジョブ型人事指針」が公表されました。日本企業が競争力を維持するためにジョブ型人事の導入を促すことが目的で、その意義や導入事例が紹介されています。ジョブ型人事の基礎となる「ジョブ」や「スキル」の整理、またスキルマップの活用方法について、慶應義塾大学大学院 特任教授の岩本隆先生に解説いただきました。
《詳細はこちら》
■CMOからCGOへ(2024.09.18公開)
2024年に米国企業で最も速く増えるといわれている役職「CGO(最高事業成長責任者)」。CMOに代わって設置されることもあり、企業全体の成長を統括するポジションです。マーケティングにとどまらず、市場を創出し、事業を成長させる役割を担います。日本企業でも少しずつ導入が進むCGOとは。
《詳細はこちら》
■中堅企業元年(2024.08.21公開)
2024年は「中堅企業」を重点的に支援するための改正法が成立した「中堅企業元年」。そのうち、賃上げや国内での設備投資に積極的な企業は「特定中堅企業」と位置付け、法人税などが優遇されます。そうした中堅企業が今後、人的資本を強化するに当たっては、マーケティングや研究開発の人材が重要となります。
《詳細はこちら》
■C-Suite 3.0(2024.08.07公開)
C-Suite(Cスイート)とは、CXOと呼ばれるコーポレート・エグゼクティブを指します。1920年代に導入が始まり、1世紀を経た現在では、CXO間の連携が重視される「C-Suite 3.0時代」に突入しました。この時代においては、次世代の経営人材である「π型人材」の重要性がますます高まっています。CXOの役割と「π型人材」の必要性について解説します。
《詳細はこちら》
■パブリックアフェアーズ(2024.07.17公開)
マーケティングの重要な役割の1つに「市場創造」があります。特にカーボンニュートラルなどの社会課題を解決するための市場を創造するには、世の中との関係を築く「PR」と、政策関係者との関係を築く「GR」の両方が必要です。これらを統合した「パブリックアフェアーズ」という考え方が注目されています。日本におけるパブリックアフェアーズの考え方とその重要性を解説します。
《詳細はこちら》
■経営におけるPRの重要性の高まり(2024.07.03公開)
現代のビジネスにおいて、PRは経営に欠かせない要素となっています。日本では「PR」は「宣伝」として理解されがちですが、本来はもっと広い意味を持ち、経営戦略の一環として重要視されています。米国ではMBAプログラムにもPRが含まれており、その重要性が強調されています。経営におけるPRの役割とその重要性を解説します。
《詳細はこちら》
■採用ブランドを高めるための人的資本開示(2024.06.19公開)
人的資本開示が国内外で進んでいます。日本では資本市場だけでなく、労働市場に向けた情報開示の重要性が高まっています。採用ブランドの構築には、適切な人的資本開示が不可欠であり、全ての従業員が自社の人的資本経営についての物語(ナラティブ)を共有することが求められます。
《詳細はこちら》
■フリーランス新法(2024.06.05公開)
通称「フリーランス新法」が2024年11月に施行されます。この法律は、フリーランスとの取引適正化と就業環境整備を目指し、フリーランスと取引する事業者に対して、給付内容の明示、ハラスメント対策、中途解除の事前予告などを求めています。法律の制定経緯とその内容を詳しく解説します。
《詳細はこちら》
■キャリアマップ(2024.05.15公開)
ギャラップ社が定義した「ウェルビーイングの5つの構成要素」のうち、最も大きく寄与するのが「キャリアウェルビーイング」であるという研究結果があります。キャリアウェルビーイングを高めるためには、「キャリアマップ」の活用が不可欠です。
《詳細はこちら》
■労働人口問題(2024.05.01公開)
2024年現在、日本における労働人口不足は、あらゆる企業にとって深刻な経営課題です。10~20年後には、人工知能やロボットで労働人口を補うというシナリオも考えられていますが、その他にどのような施策があり得るのでしょうか。労働人口問題の概況と今後の展望を解説します。
《詳細はこちら》
■スキル標準の活用に向けて(2024.03.20公開)
スキルベース採用の実現に向けて、「スキル標準」の活用が欧米を中心に進んでいます。スキル標準とは、企業や業界を超えて共通で利用できるスキルマップのことを指します。日本でもスキル標準は策定されていますが、その活用はまだ初期段階です。今後の活用推進の取り組みと見通しを解説します。
《詳細はこちら》
■スキルのデジタル証明(2024.03.06公開)
「スキルベース採用」が活発化する中で、個人が持つスキルを証明する手段として「オープンバッジ」の利用が進んでいます。オープンバッジとは何か、また採用に活用する際に採用担当者が知っておくべきポイントについて解説します。
《詳細はこちら》
■採用アナリティクスツール(2024.02.21公開)
「採用活動のボトルネックとなっている工程を特定したい」「採用経路別のコストや成果を明確にしたい」などのニーズに応えるため、人材採用の成果を高める採用アナリティクスツールが注目されています。近年、これらのツールの市場は急速に拡大しており、その現状と全体像を解説します。
《詳細はこちら》
■人材採用の基本メトリック(2024.02.07公開)
ISOは、人材採用を定量的に評価するための基本メトリックを示しています。「惹きつける/発掘する/査定する/雇用する」という人材採用の4側面をどのように測定するべきか、その指標について解説します。
《詳細はこちら》
■人材採用の国際標準化(2024.01.17公開)
人的資本報告のガイドライン(ISO 30414)をはじめ、人材分野における国際規格の開発が進んでいます。これらの国際標準は、人材採用の戦略策定に役立てられており、「Attract(惹きつける)」「Source(発掘する)」など、採用の各側面のROIを定量化して人材採用力を高めるために活用されています。人材採用の国際標準化の全体像を解説します。
《詳細はこちら》

