産業人材育成プラン
岩本 隆 2025.07.16
- 人事
- 採用
- 業界動向
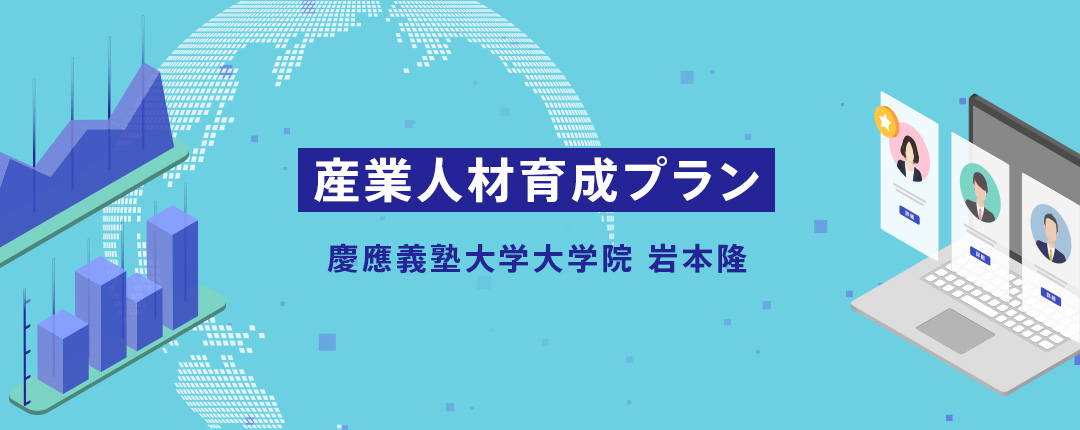
2025年6月13日に、『経済財政運営と改革の基本方針2025~「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ~』(骨太方針2025)が閣議決定されて公表されたと同時に、『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版』が新しい資本主義実現本部によって公表された(※1)。
新しい資本主義実現本部の設置は2021年10月15日に閣議決定され、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとした新しい資本主義を実現していくために内閣に設置され、それに向けたビジョンを示し、その具体化を進めるため、新しい資本主義実現会議が2025年6月末時点で合計36回開催されている。
『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版』では、産業人材政策のひとつとして「産業人材育成プラン」が示された。2025年2月に開催された新しい資本主義実現会議において、石破総理から「文部科学大臣と経済産業大臣を中心に産業人材育成のためのプランを、2025年6月を目処に具体化するように」と指示があり、2025年4月7日と2025年5月8日に意見交換会が開催され、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画にまとめられた。日本の経済・社会のニーズと人材供給の現況に大きなギャップがあり、さらに、今後大きく産業構造が変化し、就業構造に大きな変化がもたらされることが想定されるため、産業人材育成プランが策定された。
具体的には、以下の産業構造の変化に応じた、就業構造の変化を踏まえた人材育成が求められる。
(1)DXによるサービス化などで高付加価値化する「製造X(トランスフォーメーション)」
(2)情報通信業・専門サービス業の成長産業化
(3)省力化投資を活用して高付加価値化する「アドバンスト・エッセンシャルサービス」化
産業人材育成プランの実行において、関係省庁が連携して以下の取り組みを行っていく。
(1)産学協働での地域毎の人材ニーズの明確化や人材育成の連携体制の整備
都道府県などの地域ごとに、各地域における大学・高専などを中心とした産業人材育成の取り組み方針について、産学官金労などの関係者で議論・推進する「地域構想推進プラットフォーム」を構築する。
(2)各教育段階における産業人材の育成に向けた教育プログラムの充実
●初等中等教育段階
産業人材育成に向けた教育プログラムの充実のため、教育機関側が産業側に求めるリソースや産業界が提供し得るリソースについて、双方のコーディネートを行いながらマッチングを促進する仕組みの構築に向けて、2025年度中に検討する。
●高校教育段階
国が基本的な方針を示し、都道府県が自ら作成する実行計画に基づく改革を支援する仕組みづくりを進め、探求・文理横断・実践的な学びの充実、グローバル人材やDX・AI・半導体・コンテンツ産業などの人材育成、普通科改革などを通じた高校の特色化・魅力化を図る。
●高専・大学段階
「成長分野をけん引する大学・高専の機能強化に向けた基金」による事業などを活用し、高専の新設などへの支援や、寄付講座や共同研究などの実施も含め、企業からの資金提供や人材の派遣・交流など、産業界と連携した取り組みを促すことにより、成長分野への学部・学科の再編などを進める。
●専門学校
今後の急激な技術変化を踏まえて、教育内容を迅速にアップデートするとともに、アドバンスト・エッセンシャルワーカー(デジタル技術なども活用して現在よりも高い賃金を得るエッセンシャルワーカー)などを養成するリカレント教育のプログラム開発などを支援する。
(3)産業界から教育機関への資金提供・共同でのプログラム開発の促進
「地方創生に不可欠な地域での人材育成」、「産業界と連携した学部・学科の新設などに係る設置認可手続き」、「高専におけるアントレプレナーシップ教育の充実」、「エンジニアなども含めたイノベーションを支える高度人材の確保」、「民間企業が博士人材を採用しやすい環境の整備」、「高卒採用における一人一社制の廃止」などに対する施策を実行する。
今後の産業構造の変化に対応した、日本社会全体の人材の最適配置やそのための人材育成が急務となっており、そのためのアクションを日本全体で起こしていくことが求められる。
※1:新しい資本主義実現本部「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」内閣官房Webサイト(2025年/https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html#2025_head)
新しい資本主義実現本部の設置は2021年10月15日に閣議決定され、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとした新しい資本主義を実現していくために内閣に設置され、それに向けたビジョンを示し、その具体化を進めるため、新しい資本主義実現会議が2025年6月末時点で合計36回開催されている。
『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版』では、産業人材政策のひとつとして「産業人材育成プラン」が示された。2025年2月に開催された新しい資本主義実現会議において、石破総理から「文部科学大臣と経済産業大臣を中心に産業人材育成のためのプランを、2025年6月を目処に具体化するように」と指示があり、2025年4月7日と2025年5月8日に意見交換会が開催され、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画にまとめられた。日本の経済・社会のニーズと人材供給の現況に大きなギャップがあり、さらに、今後大きく産業構造が変化し、就業構造に大きな変化がもたらされることが想定されるため、産業人材育成プランが策定された。
具体的には、以下の産業構造の変化に応じた、就業構造の変化を踏まえた人材育成が求められる。
(1)DXによるサービス化などで高付加価値化する「製造X(トランスフォーメーション)」
(2)情報通信業・専門サービス業の成長産業化
(3)省力化投資を活用して高付加価値化する「アドバンスト・エッセンシャルサービス」化
産業人材育成プランの実行において、関係省庁が連携して以下の取り組みを行っていく。
(1)産学協働での地域毎の人材ニーズの明確化や人材育成の連携体制の整備
都道府県などの地域ごとに、各地域における大学・高専などを中心とした産業人材育成の取り組み方針について、産学官金労などの関係者で議論・推進する「地域構想推進プラットフォーム」を構築する。
(2)各教育段階における産業人材の育成に向けた教育プログラムの充実
●初等中等教育段階
産業人材育成に向けた教育プログラムの充実のため、教育機関側が産業側に求めるリソースや産業界が提供し得るリソースについて、双方のコーディネートを行いながらマッチングを促進する仕組みの構築に向けて、2025年度中に検討する。
●高校教育段階
国が基本的な方針を示し、都道府県が自ら作成する実行計画に基づく改革を支援する仕組みづくりを進め、探求・文理横断・実践的な学びの充実、グローバル人材やDX・AI・半導体・コンテンツ産業などの人材育成、普通科改革などを通じた高校の特色化・魅力化を図る。
●高専・大学段階
「成長分野をけん引する大学・高専の機能強化に向けた基金」による事業などを活用し、高専の新設などへの支援や、寄付講座や共同研究などの実施も含め、企業からの資金提供や人材の派遣・交流など、産業界と連携した取り組みを促すことにより、成長分野への学部・学科の再編などを進める。
●専門学校
今後の急激な技術変化を踏まえて、教育内容を迅速にアップデートするとともに、アドバンスト・エッセンシャルワーカー(デジタル技術なども活用して現在よりも高い賃金を得るエッセンシャルワーカー)などを養成するリカレント教育のプログラム開発などを支援する。
(3)産業界から教育機関への資金提供・共同でのプログラム開発の促進
「地方創生に不可欠な地域での人材育成」、「産業界と連携した学部・学科の新設などに係る設置認可手続き」、「高専におけるアントレプレナーシップ教育の充実」、「エンジニアなども含めたイノベーションを支える高度人材の確保」、「民間企業が博士人材を採用しやすい環境の整備」、「高卒採用における一人一社制の廃止」などに対する施策を実行する。
今後の産業構造の変化に対応した、日本社会全体の人材の最適配置やそのための人材育成が急務となっており、そのためのアクションを日本全体で起こしていくことが求められる。
※1:新しい資本主義実現本部「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」内閣官房Webサイト(2025年/https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html#2025_head)
- 【執筆者プロフィール】

-
岩本 隆(いわもと たかし)
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 講師
山形大学 客員教授
東京大学工学部金属工学科卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院工学・応用科学研究科材料学・材料工学専攻Ph.D.。日本モトローラ、日本ルーセント・テクノロジー、ノキア・ジャパン、ドリームインキュベータを経て、2012年6月より2022年3月まで慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授。2018年9月より2023年3月まで山形大学学術研究院産学連携教授、2022年12月より2025年3月まで慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授。2023年4月より慶應義塾大学大学院経営管理研究科講師、山形大学客員教授。ICT CONNECT 21理事、日本CHRO協会理事、日本パブリックアフェアーズ協会理事、SDGs Innovation HUB理事、日本DX地域創生応援団理事、オープンバッジ・ネットワーク理事、ISO/TC 260国内審議委員会副委員長などを兼任。
