ナラティブマーケティング
岩本 隆 2025.04.16
- 業界動向
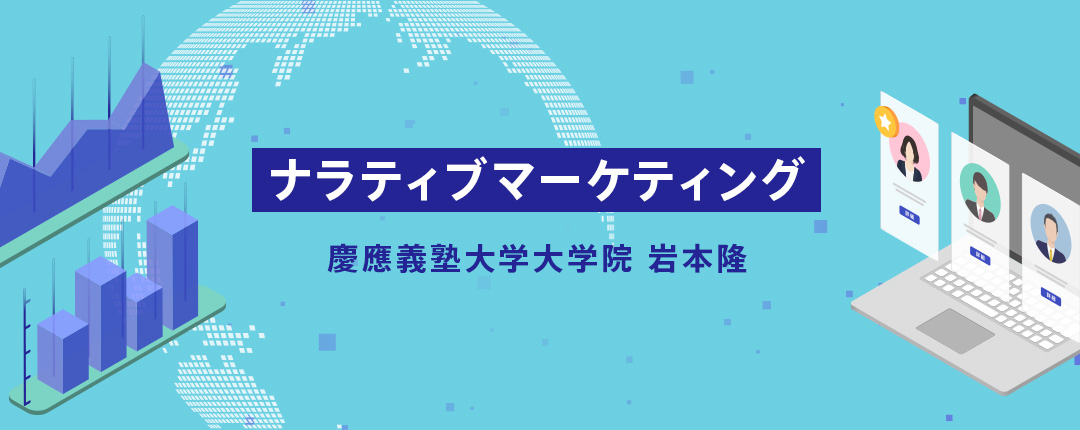
ナラティブ(Narrative)という言葉が世界的に注目を浴びており、マーケティングの領域でも「ナラティブマーケティング」の重要性が高まっている。ナラティブは「物語」を意味する言葉であるが、同じく「物語」を意味するストーリー(Story)とは意味が異なる。ストーリーは受け手を意識しない、ある意味、一方的な物語であるのに対し、ナラティブは受け手が腹落ちして行動につながる物語である。ナラティブは名詞として使われることが多いが、形容詞としても使われる。「ナラティブを語ること=ナレーション(Narration)」、「ナラティブを語る人=ナレーター(Narrator)」であり、ナラティブという言葉には馴染みがなくても、ナレーションやナレーターという言葉には馴染みがある人が多いのではないだろうか。
ナラティブについての研究は随分以前から行われており、ナラティブという言葉自体は1960年代ごろから使われるようになったと言われている。医療や臨床心理の領域でよく使われていたが、2013年にノーベル経済学賞を受賞したロバート・シラー氏が2019年10月に経済を動かすナラティブの力に着目した『Narrative Economics』という書籍(※1)を出版するなど、昨今はビジネスでも注目されるようにもなり、特にマーケティング領域でよく使われるようになってきた。
また、最近では人的資本経営の実践においてもナラティブの重要性が高まっており、筆者はこれを推進している。『Narrative Economics』の日本語版は2021年7月に出版され日本でも注目された(※2)。ロバート・シラー氏によれば、「経済ナラティブ」とは人々の経済的な判断を変える物語であり、そのような物語が、過去に共感を得て人々の判断を変え、経済活動にしばしば影響をもたらしてきた。また、2021年12月に世界経済フォーラムが出版した『The Great Narrative』という書籍が12カ国語に翻訳されてベストセラーとなり(※3)、ナラティブが世界的にも大きく注目されている。この書籍の日本語版は2022年6月に出版されている(※4)。
ナラティブマーケティングは、ユーザーが腹落ちして行動につながる物語を展開するマーケティング手法であり、インターネット検索をすると、この数年、日本語の記事や寄稿文も急増してきている。アカデミアでも、日本マーケティング学会が2017年4月に開始した「物語マーケティング研究会」を「ナラティヴ・マーケティング研究会」に名称を変更しナラティブマーケティングについての研究を推進している(※5)。名称変更の背景は、マーケティングにおいて活用される物語のうち、企業が主体的に管理・発信するコンテンツとしてのストーリーだけでなく、顧客による「物語る」という行為、すなわちナラティブに着目するよう研究フォーカスがより具体的になったということである。ナラティヴ・マーケティング研究会では以下の研究報告会がこれまで実施されている。
●2021年3月:「ナラティブ・ブランディングにおける賛否両論アプローチの事例研究」
●2022年3月:「ナラティヴ・ブランディングの構図」
●2023年3月:「ナラティヴ・アプローチ・ブランディングの構図」
●2024年3月:「コミュニティビジネスにおけるナラティヴ-YAMAP語りの変遷-」
●2025年3月:「ナラティヴ・マーケティングの可能性-カルチュラル・ブランディングにおける物語戦略-」
マーケターとしてのキャリアを歩む人たちにとって、ナラティブマーケティングは今後さらに重要なテーマになってくるであろう。
※1:Robert J. Shiller「Narrative Economics: How Stories Go Viral & Drive Major Economic Events」Princeton University Press(2019年)
※2:ロバート・J・シラー「ナラティブ経済学:経済予測の全く新しい考え方」東京経済新報社(2021年)
※3:Klaus Schwab、Thierry Malleret「The Great Narrative」Forum Publishing(2021年)
※4:クラウス・シュワブ、ティエリ・マルレ『グレート・ナラティブ 「グレート・リセット」後の物語』日経ナショナルジオグラフィック(2022年)
※5:日本マーケティング学会「ナラティヴ・マーケティング研究会」日本マーケティング学会Webサイト(2025年/https://www.j-mac.or.jp/research-project/14534/)
ナラティブについての研究は随分以前から行われており、ナラティブという言葉自体は1960年代ごろから使われるようになったと言われている。医療や臨床心理の領域でよく使われていたが、2013年にノーベル経済学賞を受賞したロバート・シラー氏が2019年10月に経済を動かすナラティブの力に着目した『Narrative Economics』という書籍(※1)を出版するなど、昨今はビジネスでも注目されるようにもなり、特にマーケティング領域でよく使われるようになってきた。
また、最近では人的資本経営の実践においてもナラティブの重要性が高まっており、筆者はこれを推進している。『Narrative Economics』の日本語版は2021年7月に出版され日本でも注目された(※2)。ロバート・シラー氏によれば、「経済ナラティブ」とは人々の経済的な判断を変える物語であり、そのような物語が、過去に共感を得て人々の判断を変え、経済活動にしばしば影響をもたらしてきた。また、2021年12月に世界経済フォーラムが出版した『The Great Narrative』という書籍が12カ国語に翻訳されてベストセラーとなり(※3)、ナラティブが世界的にも大きく注目されている。この書籍の日本語版は2022年6月に出版されている(※4)。
ナラティブマーケティングは、ユーザーが腹落ちして行動につながる物語を展開するマーケティング手法であり、インターネット検索をすると、この数年、日本語の記事や寄稿文も急増してきている。アカデミアでも、日本マーケティング学会が2017年4月に開始した「物語マーケティング研究会」を「ナラティヴ・マーケティング研究会」に名称を変更しナラティブマーケティングについての研究を推進している(※5)。名称変更の背景は、マーケティングにおいて活用される物語のうち、企業が主体的に管理・発信するコンテンツとしてのストーリーだけでなく、顧客による「物語る」という行為、すなわちナラティブに着目するよう研究フォーカスがより具体的になったということである。ナラティヴ・マーケティング研究会では以下の研究報告会がこれまで実施されている。
●2021年3月:「ナラティブ・ブランディングにおける賛否両論アプローチの事例研究」
●2022年3月:「ナラティヴ・ブランディングの構図」
●2023年3月:「ナラティヴ・アプローチ・ブランディングの構図」
●2024年3月:「コミュニティビジネスにおけるナラティヴ-YAMAP語りの変遷-」
●2025年3月:「ナラティヴ・マーケティングの可能性-カルチュラル・ブランディングにおける物語戦略-」
マーケターとしてのキャリアを歩む人たちにとって、ナラティブマーケティングは今後さらに重要なテーマになってくるであろう。
※1:Robert J. Shiller「Narrative Economics: How Stories Go Viral & Drive Major Economic Events」Princeton University Press(2019年)
※2:ロバート・J・シラー「ナラティブ経済学:経済予測の全く新しい考え方」東京経済新報社(2021年)
※3:Klaus Schwab、Thierry Malleret「The Great Narrative」Forum Publishing(2021年)
※4:クラウス・シュワブ、ティエリ・マルレ『グレート・ナラティブ 「グレート・リセット」後の物語』日経ナショナルジオグラフィック(2022年)
※5:日本マーケティング学会「ナラティヴ・マーケティング研究会」日本マーケティング学会Webサイト(2025年/https://www.j-mac.or.jp/research-project/14534/)
- 【執筆者プロフィール】

-
岩本 隆(いわもと たかし)
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 講師
山形大学 客員教授
東京大学工学部金属工学科卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院工学・応用科学研究科材料学・材料工学専攻Ph.D.。日本モトローラ、日本ルーセント・テクノロジー、ノキア・ジャパン、ドリームインキュベータを経て、2012年6月より2022年3月まで慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授。2018年9月より2023年3月まで山形大学学術研究院産学連携教授、2022年12月より2025年3月まで慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授。2023年4月より慶應義塾大学大学院経営管理研究科講師、山形大学客員教授。ICT CONNECT 21理事、日本CHRO協会理事、日本パブリックアフェアーズ協会理事、SDGs Innovation HUB理事、日本DX地域創生応援団理事、オープンバッジ・ネットワーク理事、ISO/TC 260国内審議委員会副委員長などを兼任。
