キャリア採用受け入れ準備ガイド
2020.06.02
- 採用ノウハウ
- 評価制度
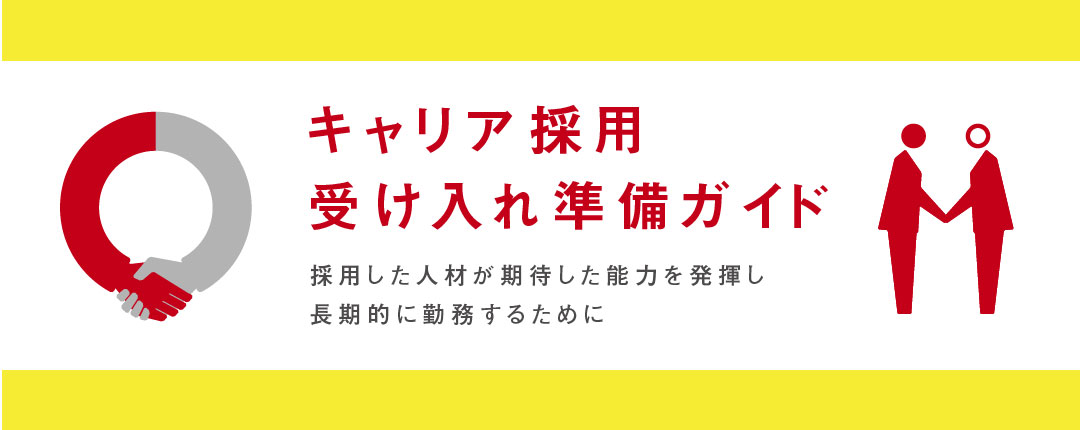
早期退職を未然に防ぐために・・・
早期退職の危機を未然に防ぐには、採用者と内定から入社後までしっかりとコミュニケーションを取り、フォローしていくことが大切です。早期退職に陥る大きな理由
●面接・内定時に説明を受けた仕事の内容や待遇面、勤務条件などに食い違いがある
●社内のコミュニケーション不足
●社内に相談できる人がいない
●会社文化への戸惑い
●短期的な成果へのプレッシャー
●セクハラ、パワハラに類似する問題 など
早期退職を予防・回避するための具体的な準備事項を、時期ごとのステップにわけてご紹介します。
入社前
□全社員に周知しましょう。採用者の「名前」「入社日」「業務内容」などを全社員に周知しましょう。全社員で採用者を温かく受け入れる体制をつくることが大切です。
□机やPC、名刺など業務に必要な備品は入社日までに準備しましょう。
入社日になにも用意されていないと、「自分は会社に受け入れてもらえるのか?」と不安に思ってしまうことがあるからです。
□入社日の業務スケジュールを決め関係者に周知しましょう。
採用者は、1日も早く職場に慣れたいと強く思っているのと同時に不安も感じています。入社日は、一番不安を感じるタイミングです。入社日は、「放置されている状態」がないように、事前に入社日の業務スケジュールを決めておくとよいでしょう。
□入社から約1カ月の間に従事する業務とスケジュールを事前に決めましょう。
なにもやることがなかったり、業務が多すぎたりすることがないように、事前にコントロールしておきましょう。
□メンターを付けることをおすすめします。
上司や人事担当者以外で、気軽に相談できるメンターを付けることをおすすめします。採用者によっては、以前に在籍した会社の「常識」を引きずっている場合もあります。仕事の進め方や社風に早く慣れてもらうためにも、気軽に相談できる環境を整えましょう。それが、より早い社内への定着、さらには早期退職を防ぐことにつながります。
□入社日の確認事項をご案内しましょう。
入社日をスムーズに迎えるために、採用者へ確認事項をご案内しましょう。
●出社時の服装(どのような服装で出社するのが適切なのか)
●出社時間(出社時間の何分前に到着するとスムーズなのか)
●誰宛に伺えばよいのか
●入社日の持参物(印鑑、年金手帳、雇用保険被保険証、住民票、銀行口座番号など)
●入社日の簡単なスケジュール(午前は入社手続き、午後は業務のオリエンテーション・研修など)
入社日
□社員に積極的に紹介をしましょう。社長や役職者、マネージャー、今後やり取りが多い社員を中心に、採用者を積極的にご紹介しましょう。
□昼食のフォローも忘れずに。
採用者がぽつんと一人で昼食を取ることがないようにフォローをしましょう。
入社から2 週間程度
□入社から約1カ月の間に従事する業務とスケジュールについてオリエンテーションをしましょう。所属部署や関係者と事前に確認した業務内容やスケジュールを伝えることで、実際の仕事に対する不安を和らげてください。
□会社のルールを説明する場をつくりましょう。
「出退勤の管理」「よく使うシステム」「会社独自のルール」など、既に働いている社員にとっては当たり前のことでも、採用者にとっては初めてのことばかりです。総務の方にご協力をいただくなどして、会社の基本的なルールを説明する場をつくりましょう。
□入社直後に研修を行うこともおすすめします。
たとえ即戦力の採用であったとしても、入社する会社での実務経験は当然ながらありません。会社によって業務の進め方もさまざまですので、研修を通して自社のやり方をいち早く覚えてもらうことが即戦力につながります。入社直後は、仕事の進め方などに不安を抱くものです。安心感を与える上でも研修は効果的です。
入社から6 カ月間程度
□日報や週報などで業務状況を把握しましょう。採用者に日報や週報などで業務状況を報告してもらうことをおすすめします。「困っていることはないか」「トラブルはないか」「業務量が多すぎる・少なすぎることはないか」など、業務状況を日々チェックし、状況に応じてフォローするように心がけましょう。
□定期的に上司もしくは人事担当による個別面談を行いましょう。
入社後、問題がないように見えても実は問題を抱えている場合もあります。入社当初は遠慮して本音で話をすることができないことも多々あります。定期的に上司や人事担当が個別で話をする場をつくってください。相談しやすい雰囲気づくりを心がけることにより、お互いの勘違い・思い違いによる早期退職やトラブルを未然に防ぐことにつながります。個別面談のタイミングは、入社1週間後、2週間後、1カ月後、2カ月後……といように、入社直後は頻繁に、その後は1カ月間隔で行うと効果的です。
□メンターによるフォローも大切です。
正式な場ではなくても結構です。食事やお茶を一緒にするなどして、採用者が不安に思っていることなどを気軽に相談できる環境づくりを心がけましょう。
□短期的な成果よりも中・長期的な活躍を大切にしましょう。
キャリア採用者はすぐの成果を求められがちですが、最初から活躍できる人はいません。たとえ即戦力の採用であったとしても、入社する会社での実務経験は当然ながらありません。会社によって業務の進め方もさまざまです。徐々に会社のやり方に慣れて、中・長期的に活躍ができるようにフォローをしましょう。
