経済産業政策新機軸によって実現を目指す2040年の就業構造
岩本 隆 2025.09.12
- 人事
- 人的資本
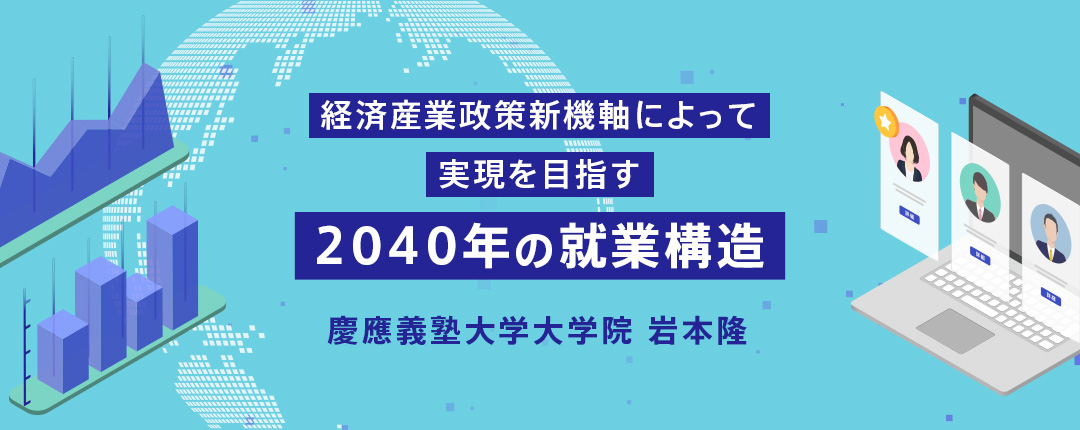
2021年6月4日に経済産業省産業構造審議会にて経済産業政策の新機軸の考え方が提示され、2021年11月19日より産業構造審議会経済産業政策新機軸部会において経済産業政策の新機軸の議論がなされており、これまで以下の報告書が公表されている。
・2022年6月13日:「経済産業政策新機軸部会 第1次中間整理」
・2023年6月27日:「経済産業政策新機軸部会 第2次中間整理」
・2024年6月7日:「経済産業政策新機軸部会 第3次中間整理」
・2025年6月3日:「経済産業政策新機軸部会 第4次中間整理~成長投資が導く2040年の産業構造~」
経済産業政策の新機軸と過去の産業政策との違いは以下である。
・~1980年代:官が主導する伝統的産業政策
・1990年代~2010年代:官は民を邪魔しないことに徹する新自由主義的政策
・2021年~:社会・経済課題解決に向けて、官も民も一歩前に出て、あらゆる政策を総動員する新たな産業政策=新機軸
第3次中間整理から第4次中間整理にかけては、30年続いたコストカット型の縮み思考から、投資と賃上げが牽引する成長思考に転換するため、2年のプロジェクトとして、「人口減少下でも一人一人が豊かになれる日本の将来見通し」づくりに着手してきた。その中で2040年にあるべき就業構造も分析されており、図表1に職種別の2040年の労働需要と現在のトレンドの延長で考えた場合の労働供給予測を示す(※1)。生成AI、ロボット等の省力化に伴い、事務、販売、サービス等の従事者は約300万人の余剰が生じる可能性がある一方、多くの産業で研究者/技術者は不足傾向で、とりわけ、各産業でAIやロボット等の活用を担う人材は合計で約300万人不足するリスクがある。
・2022年6月13日:「経済産業政策新機軸部会 第1次中間整理」
・2023年6月27日:「経済産業政策新機軸部会 第2次中間整理」
・2024年6月7日:「経済産業政策新機軸部会 第3次中間整理」
・2025年6月3日:「経済産業政策新機軸部会 第4次中間整理~成長投資が導く2040年の産業構造~」
経済産業政策の新機軸と過去の産業政策との違いは以下である。
・~1980年代:官が主導する伝統的産業政策
・1990年代~2010年代:官は民を邪魔しないことに徹する新自由主義的政策
・2021年~:社会・経済課題解決に向けて、官も民も一歩前に出て、あらゆる政策を総動員する新たな産業政策=新機軸
第3次中間整理から第4次中間整理にかけては、30年続いたコストカット型の縮み思考から、投資と賃上げが牽引する成長思考に転換するため、2年のプロジェクトとして、「人口減少下でも一人一人が豊かになれる日本の将来見通し」づくりに着手してきた。その中で2040年にあるべき就業構造も分析されており、図表1に職種別の2040年の労働需要と現在のトレンドの延長で考えた場合の労働供給予測を示す(※1)。生成AI、ロボット等の省力化に伴い、事務、販売、サービス等の従事者は約300万人の余剰が生じる可能性がある一方、多くの産業で研究者/技術者は不足傾向で、とりわけ、各産業でAIやロボット等の活用を担う人材は合計で約300万人不足するリスクがある。

(出所:参考資料※1より筆者作成)
これらのミスマッチを解消するために、これから以下の施策に取り組む(※2)。
・徹底した人手不足への対応
「省力化投資の促進」、「企業価値向上につながる多様な人材の活躍支援」、「時間的制約のある労働者の活躍支援」、「中小企業等向けの人材活用ガイドラインの普及」、「人的資本経営の更なる普及・取組の深化」等
・賃上げに向けた取組の強化
「中小企業の価格転嫁対策・取引適正化の推進」、「賃上げ促進税制の周知・広報」等
・内部労働市場・外部労働市場の活性化による労働移動の円滑化
「高度外国人材の活躍」、「人的資本経営の更なる普及・取組の深化」等
・官民を挙げたリスキリング・人材育成
「就業構造推計と産業人材教育の充実」、「博士人材の育成・活躍促進」、「初等中等教育の連携促進」、「デジタル人材育成の促進」、「人的資本経営の更なる普及・取組の深化」等
産業構造と労働需要は表裏一体であり、産官学が連携して、産業構造の変革とそれを実現する労働供給を可能にするための労働移動や人材育成を行うことが求められる。
※1:経済産業省産業構造審議会経済産業政策新機軸部会「経済産業政策新機軸部会 第4次中間整理 参考資料集~成長投資が導く2040年の産業構造~」経済産業省Webサイト(2025年/https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/pdf/20250603_4.pdf)
※2:経済産業省産業構造審議会経済産業政策新機軸部会「経済産業政策新機軸部会 第4次中間整理~成長投資が導く2040年の産業構造~」経済産業省Webサイト(2025年/https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/pdf/20250603_1.pdf)
・徹底した人手不足への対応
「省力化投資の促進」、「企業価値向上につながる多様な人材の活躍支援」、「時間的制約のある労働者の活躍支援」、「中小企業等向けの人材活用ガイドラインの普及」、「人的資本経営の更なる普及・取組の深化」等
・賃上げに向けた取組の強化
「中小企業の価格転嫁対策・取引適正化の推進」、「賃上げ促進税制の周知・広報」等
・内部労働市場・外部労働市場の活性化による労働移動の円滑化
「高度外国人材の活躍」、「人的資本経営の更なる普及・取組の深化」等
・官民を挙げたリスキリング・人材育成
「就業構造推計と産業人材教育の充実」、「博士人材の育成・活躍促進」、「初等中等教育の連携促進」、「デジタル人材育成の促進」、「人的資本経営の更なる普及・取組の深化」等
産業構造と労働需要は表裏一体であり、産官学が連携して、産業構造の変革とそれを実現する労働供給を可能にするための労働移動や人材育成を行うことが求められる。
※1:経済産業省産業構造審議会経済産業政策新機軸部会「経済産業政策新機軸部会 第4次中間整理 参考資料集~成長投資が導く2040年の産業構造~」経済産業省Webサイト(2025年/https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/pdf/20250603_4.pdf)
※2:経済産業省産業構造審議会経済産業政策新機軸部会「経済産業政策新機軸部会 第4次中間整理~成長投資が導く2040年の産業構造~」経済産業省Webサイト(2025年/https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/pdf/20250603_1.pdf)
- 【執筆者プロフィール】

-
岩本 隆(いわもと たかし)
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授
東京大学工学部金属工学科卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院工学・応用科学研究科材料学・材料工学専攻Ph.D.。日本モトローラ、日本ルーセント・テクノロジー、ノキア・ジャパン、ドリームインキュベータを経て、2012年6月より2022年3月まで慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授。2018年9月より2023年3月まで山形大学学術研究院産学連携教授、2022年12月より慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授。ICT CONNECT 21理事、日本CHRO協会理事、日本パブリックアフェアーズ協会理事、SDGs Innovation HUB理事、デジタル田園都市国家構想応援団理事、オープンバッジ・ネットワーク理事、ISO/TC 260国内審議委員会副委員長などを兼任。
