スキルベース人材育成に向けた政策
岩本 隆 2025.08.04
- 人事
- 人的資本
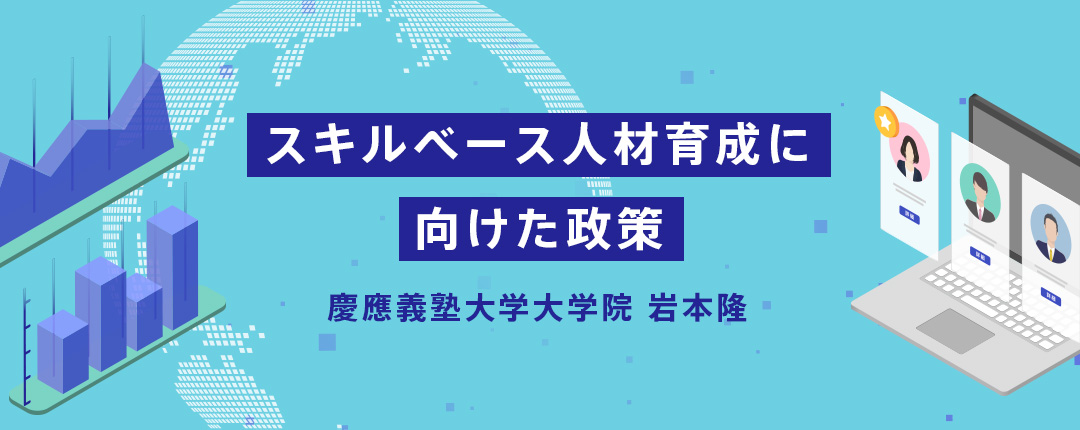
2025年5月23日に経済産業省から「Society 5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会 報告書-「スキルベースの人材育成」を目指して-」が公表された(※1)。Society 5.0は、2016年1月22日に閣議決定された「第5期科学技術基本計画」において提唱された概念で、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決とを両立する人間中心の社会」と定義されている(※2)。
そして、一般社団法人日本経済団体連合会が2018年11月13日に公表した「Society 5.0-ともに創造する未来-」では、Society 5.0を「創造社会」と呼称することが提唱され、「デジタル革新と多様な人々の想像・創造力の融合によって、社会の課題を解決し、価値を創造する社会」とされた(※3)。Society 5.0とは、要は、これから日本としてつくっていきたいと考えている社会のことである。
Society 5.0を実現するためには日本企業全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)が不可欠であるが、企業がDXに取り組まない理由の上位に人材育成が進んでいないことが挙げられている。以下に企業がDXに取り組まない理由の上位4つを記す。
1. DX戦略の立案や統括を行う人材の不足
2. DXを現場で推進、実行する人材の不足
3. 知識や情報の不足
4. スキルの不足
これまで経済産業省として、スキル可視化のための「デジタルスキル標準」の策定、「学びDX(デラックス)」、「学びDX Quest」などの学習コンテンツや実践的教育の提供、能力保証・効果測定のための「情報処理技術者試験」などの政策を打ってきており、官民によるリスキリングの供給面は充実してきたが、需要側である学ぶ人々の現状に関する可視化がなされていないことが大きな課題となっている。
そのため、さまざまな政策を共通プラットフォーム上で一元的に運営し、官民の保有する関連データを集積することが必要であり、個人のデジタルスキル情報の蓄積・可視化により、デジタル技術の継続的な学びを実現するとともに、スキル情報を広く労働市場で活用するための仕組み(=スキル情報基盤)として独立行政法人情報処理推進機構(IPA:Information-technology Promotion Agency, Japan)においてデジタル人材育成・DX推進プラットフォーム(仮称)」を検討することになった。このスキル情報基盤では以下の価値を提供する。
(1) スキル情報の蓄積・可視化
・保有スキルや資格情報をデジタル資格証明(デジタルクレデンシャル)として発行。
・IPA提供サービス、IPAと連携する試験・資格・学習サービスのスキル情報の公的証明機能により、スキルの共通言語化に貢献。
(2) 動的なスキル把握
・従来試験が提供する「静的な知識・スキルの評価」に加え、「動的で実践的な評価」のニーズにも適合。
・スキル情報の蓄積を前提に、試験の合否を超えたアセスメントや新しいスキル習得機械のリコメンド、試験のバージョン管理も可能に。
(3) スキル情報のビッグデータ化
・市場におけるスキル習得の状況を可視化し、個人、企業におけるデジタル人材の採用・育成の参考に。
・DXに効果的な人材スキルや人材戦略などの分析、新たな教育サービスの創出に貢献。
・スキル情報等をビッグデータとして分析し、新たなスキルタクソノミー形成やデジタルスキル標準のアップデートが期待。
(4) ともに学び合うコミュニティ形成
・業種別、イシュー別のコミュニティが形成され、コミュニティ自身が課題解決に向けて活動。
・政策へのフィードバックの機会。
・次世代リーダーが最先端のデジタル技術情報に触れ、DX先進企業と交流する機会。
海外で大きく進んでいるスキルベース人材育成を日本でも強く推進するための政策が動いていくが、この流れの中で企業もスキルベース人材育成を加速することが求められる。
※1:Society 5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会 デジタル人材のスキル・学習の在り方ワーキンググループ「Society 5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会 報告書-「スキルベースの人材育成」を目指して-」経済産業省ウェブサイト(2025年/https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/society_digital/20250523_report.html)
※2:内閣府「第5期科学技術基本計画」内閣府ウェブサイト(2016年/https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html)
※3:日本経済団体連合会「Society 5.0-ともに創造する未来」日本経済団体連合会ウェブサイト(2018年/https://www.keidanren.or.jp/policy/society5.0.html)
そして、一般社団法人日本経済団体連合会が2018年11月13日に公表した「Society 5.0-ともに創造する未来-」では、Society 5.0を「創造社会」と呼称することが提唱され、「デジタル革新と多様な人々の想像・創造力の融合によって、社会の課題を解決し、価値を創造する社会」とされた(※3)。Society 5.0とは、要は、これから日本としてつくっていきたいと考えている社会のことである。
Society 5.0を実現するためには日本企業全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)が不可欠であるが、企業がDXに取り組まない理由の上位に人材育成が進んでいないことが挙げられている。以下に企業がDXに取り組まない理由の上位4つを記す。
1. DX戦略の立案や統括を行う人材の不足
2. DXを現場で推進、実行する人材の不足
3. 知識や情報の不足
4. スキルの不足
これまで経済産業省として、スキル可視化のための「デジタルスキル標準」の策定、「学びDX(デラックス)」、「学びDX Quest」などの学習コンテンツや実践的教育の提供、能力保証・効果測定のための「情報処理技術者試験」などの政策を打ってきており、官民によるリスキリングの供給面は充実してきたが、需要側である学ぶ人々の現状に関する可視化がなされていないことが大きな課題となっている。
そのため、さまざまな政策を共通プラットフォーム上で一元的に運営し、官民の保有する関連データを集積することが必要であり、個人のデジタルスキル情報の蓄積・可視化により、デジタル技術の継続的な学びを実現するとともに、スキル情報を広く労働市場で活用するための仕組み(=スキル情報基盤)として独立行政法人情報処理推進機構(IPA:Information-technology Promotion Agency, Japan)においてデジタル人材育成・DX推進プラットフォーム(仮称)」を検討することになった。このスキル情報基盤では以下の価値を提供する。
(1) スキル情報の蓄積・可視化
・保有スキルや資格情報をデジタル資格証明(デジタルクレデンシャル)として発行。
・IPA提供サービス、IPAと連携する試験・資格・学習サービスのスキル情報の公的証明機能により、スキルの共通言語化に貢献。
(2) 動的なスキル把握
・従来試験が提供する「静的な知識・スキルの評価」に加え、「動的で実践的な評価」のニーズにも適合。
・スキル情報の蓄積を前提に、試験の合否を超えたアセスメントや新しいスキル習得機械のリコメンド、試験のバージョン管理も可能に。
(3) スキル情報のビッグデータ化
・市場におけるスキル習得の状況を可視化し、個人、企業におけるデジタル人材の採用・育成の参考に。
・DXに効果的な人材スキルや人材戦略などの分析、新たな教育サービスの創出に貢献。
・スキル情報等をビッグデータとして分析し、新たなスキルタクソノミー形成やデジタルスキル標準のアップデートが期待。
(4) ともに学び合うコミュニティ形成
・業種別、イシュー別のコミュニティが形成され、コミュニティ自身が課題解決に向けて活動。
・政策へのフィードバックの機会。
・次世代リーダーが最先端のデジタル技術情報に触れ、DX先進企業と交流する機会。
海外で大きく進んでいるスキルベース人材育成を日本でも強く推進するための政策が動いていくが、この流れの中で企業もスキルベース人材育成を加速することが求められる。
※1:Society 5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会 デジタル人材のスキル・学習の在り方ワーキンググループ「Society 5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会 報告書-「スキルベースの人材育成」を目指して-」経済産業省ウェブサイト(2025年/https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/society_digital/20250523_report.html)
※2:内閣府「第5期科学技術基本計画」内閣府ウェブサイト(2016年/https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html)
※3:日本経済団体連合会「Society 5.0-ともに創造する未来」日本経済団体連合会ウェブサイト(2018年/https://www.keidanren.or.jp/policy/society5.0.html)
- 【執筆者プロフィール】

-
岩本 隆(いわもと たかし)
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 講師
山形大学 客員教授
東京大学工学部金属工学科卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院工学・応用科学研究科材料学・材料工学専攻Ph.D.。日本モトローラ、日本ルーセント・テクノロジー、ノキア・ジャパン、ドリームインキュベータを経て、2012年6月より2022年3月まで慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授。2018年9月より2023年3月まで山形大学学術研究院産学連携教授、2022年12月より2025年3月まで慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授。2023年4月より慶應義塾大学大学院経営管理研究科講師、山形大学客員教授。ICT CONNECT 21理事、日本CHRO協会理事、日本パブリックアフェアーズ協会理事、SDGs Innovation HUB理事、日本DX地域創生応援団理事、オープンバッジ・ネットワーク理事、ISO/TC 260国内審議委員会副委員長などを兼任。
