マイクロクレデンシャル
岩本 隆 2024.11.06
- 人的資本
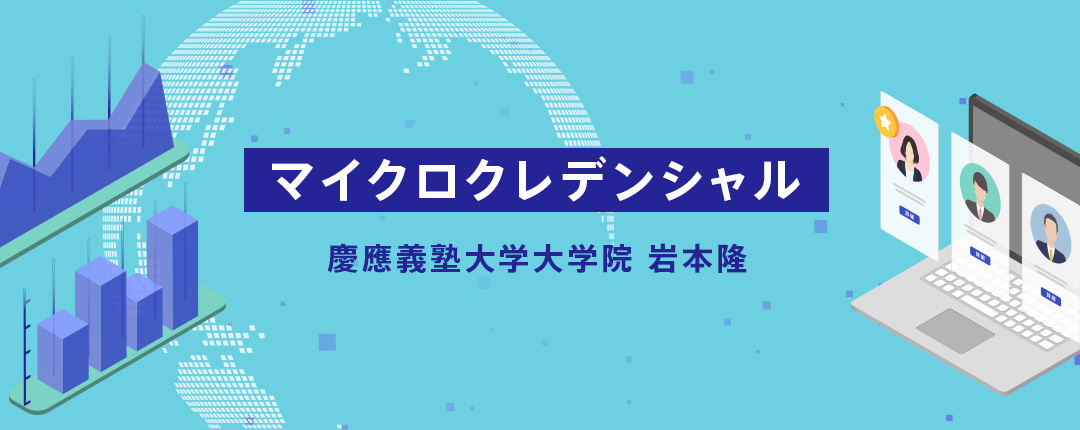
筆者は一般社団法人オープンバッジ・ネットワーク オープンバッジ大賞実行委員会が主催する「オープンバッジ大賞」の審査委員長を務めている。「オープンバッジ大賞」は文部科学省、経済産業省、デジタル庁、東京商工会議所が後援し、9つの団体が協賛する表彰イベントである。オープンバッジは、知識・スキル・経験などのデジタル証明の国際規格で、2023年より年に一度オープンバッジを先進的に活用している団体を表彰しており、2回目の2024年も受賞団体が決定した。以下に「第2回 オープンバッジ大賞」受賞団体を記す。
【大賞】
・サイバー大学:『サイバー大学マイクロクレデンシャル』
【優秀賞】
・日本新薬(企業部門):『DX Challenger』
・関西学院大学(教育機関部門):『Canada-Japan “Cross-Cultural College” Certificate Program』
・ディジタルグロースアカデミア(研修機関部門):『「みんなデ」オープンバッジ』
【奨励賞】
・住友ゴム工業(企業部門):『第1回AIコンペティション1位(1st AI Competition 1st Prize)』
・トヨタ自動車(企業部門):『デジタル価値創出人材Lv.1』
・日本電気(企業部門):『NEC DX人材_コンサルタント』
【ASIA PACIFIC賞 GOLD】
・ソウル市城北青少年センター(自治体部門):『青少年能力開発プログラム』
【ASIA PACIFIC賞 SILVER】
・IC-PBL共有・協力コンソーシアム(教育機関部門):『産学連携PBL教育プログラム』
・KT(Korea Telecom)(研修機関部門):『AICE(みんなのAI資格)』
「第2回 オープンバッジ大賞」では10団体が受賞した。第1回と比べての変化としては、企業からの応募が増えたこと、つまり、企業でのオープンバッジ活用が活発化していることと、マイクロクレデンシャル活用の事例が出たことであり、日本の大学で初めてマイクロクレデンシャルを導入したサイバー大学が大賞を受賞した。
マイクロクレデンシャルは、学習内容をより細分化した単位ごとの履修証明を指すため、個人が持つスキルやケイパビリティをより細分化して証明ができる。2022年にUNESCO(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization:国連教育科学文化機関)が各国の定義を踏まえてまとめた、マイクロクレデンシャルの定義は以下となる(※1)。
1.学習者が知っていること、理解していること、またはできることを証明する、対象が重点化された学修成果の記録である。
2.明確に定義された基準に基づいたアセスメントを含み、信頼できる提供者によって授与される。
3.単独で価値を持ち、さらに他のマイクロクレデンシャルまたはマクロクレデンシャル(※2)の一部を構成したり、それらを補完したりすることができる(既修得学習の認定も含める)。
4.関連する質保証が求める基準を満たす。
日本では2023年8月18日に、大学の国際化促進フォーラム、Japan Virtual Campus運営委員会、一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会の3団体で、「マイクロクレデンシャル共同WG」が設立され、2024年4月11日に、『マイクロクレデンシャルのフレームワーク ver.1.0』と『マイクロクレデンシャルのデジタル証明をデジタルバッジで発行するためのガイドライン ver.1.0』を公表した。マイクロクレデンシャルにオープンバッジを発行するためには、これらのフレームワークやガイドラインに準拠していれば良い。
マイクロクレデンシャルはスキルを細分化できるため、現在、世界でも日本でも広がってきているスキルベースの組織マネジメントに応用できる。さらに、持ち運びができるため、個人にとっても、新たな仕事の機会を得る際に活かすことができる。2024年は、日本は「マイクロクレデンシャル元年」になると言われていたが、その予測通りに具体的な活用事例が注目を浴びてきたことで、今後ますますマイクロクレデンシャルの活用が広がることが期待される。
●「オープンバッジ大賞」Webサイト:https://www.openbadge.or.jp/award/
●「マイクロクレデンシャル共同WG」Webサイト:https://micro-credential-jwg.org/
※1:UNESCO「Towards a common definition of micro-credentials」UNESCO Webサイト(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381668)
※2:大学の学士号や修士号という学位プログラムなど、大きな単位での学習内容の認証のこと
【大賞】
・サイバー大学:『サイバー大学マイクロクレデンシャル』
【優秀賞】
・日本新薬(企業部門):『DX Challenger』
・関西学院大学(教育機関部門):『Canada-Japan “Cross-Cultural College” Certificate Program』
・ディジタルグロースアカデミア(研修機関部門):『「みんなデ」オープンバッジ』
【奨励賞】
・住友ゴム工業(企業部門):『第1回AIコンペティション1位(1st AI Competition 1st Prize)』
・トヨタ自動車(企業部門):『デジタル価値創出人材Lv.1』
・日本電気(企業部門):『NEC DX人材_コンサルタント』
【ASIA PACIFIC賞 GOLD】
・ソウル市城北青少年センター(自治体部門):『青少年能力開発プログラム』
【ASIA PACIFIC賞 SILVER】
・IC-PBL共有・協力コンソーシアム(教育機関部門):『産学連携PBL教育プログラム』
・KT(Korea Telecom)(研修機関部門):『AICE(みんなのAI資格)』
「第2回 オープンバッジ大賞」では10団体が受賞した。第1回と比べての変化としては、企業からの応募が増えたこと、つまり、企業でのオープンバッジ活用が活発化していることと、マイクロクレデンシャル活用の事例が出たことであり、日本の大学で初めてマイクロクレデンシャルを導入したサイバー大学が大賞を受賞した。
マイクロクレデンシャルは、学習内容をより細分化した単位ごとの履修証明を指すため、個人が持つスキルやケイパビリティをより細分化して証明ができる。2022年にUNESCO(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization:国連教育科学文化機関)が各国の定義を踏まえてまとめた、マイクロクレデンシャルの定義は以下となる(※1)。
1.学習者が知っていること、理解していること、またはできることを証明する、対象が重点化された学修成果の記録である。
2.明確に定義された基準に基づいたアセスメントを含み、信頼できる提供者によって授与される。
3.単独で価値を持ち、さらに他のマイクロクレデンシャルまたはマクロクレデンシャル(※2)の一部を構成したり、それらを補完したりすることができる(既修得学習の認定も含める)。
4.関連する質保証が求める基準を満たす。
日本では2023年8月18日に、大学の国際化促進フォーラム、Japan Virtual Campus運営委員会、一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会の3団体で、「マイクロクレデンシャル共同WG」が設立され、2024年4月11日に、『マイクロクレデンシャルのフレームワーク ver.1.0』と『マイクロクレデンシャルのデジタル証明をデジタルバッジで発行するためのガイドライン ver.1.0』を公表した。マイクロクレデンシャルにオープンバッジを発行するためには、これらのフレームワークやガイドラインに準拠していれば良い。
マイクロクレデンシャルはスキルを細分化できるため、現在、世界でも日本でも広がってきているスキルベースの組織マネジメントに応用できる。さらに、持ち運びができるため、個人にとっても、新たな仕事の機会を得る際に活かすことができる。2024年は、日本は「マイクロクレデンシャル元年」になると言われていたが、その予測通りに具体的な活用事例が注目を浴びてきたことで、今後ますますマイクロクレデンシャルの活用が広がることが期待される。
●「オープンバッジ大賞」Webサイト:https://www.openbadge.or.jp/award/
●「マイクロクレデンシャル共同WG」Webサイト:https://micro-credential-jwg.org/
※1:UNESCO「Towards a common definition of micro-credentials」UNESCO Webサイト(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381668)
※2:大学の学士号や修士号という学位プログラムなど、大きな単位での学習内容の認証のこと
- 【執筆者プロフィール】

-
岩本 隆(いわもと たかし)
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授
東京大学工学部金属工学科卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院工学・応用科学研究科材料学・材料工学専攻Ph.D.。日本モトローラ、日本ルーセント・テクノロジー、ノキア・ジャパン、ドリームインキュベータを経て、2012年6月より2022年3月まで慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授。2018年9月より2023年3月まで山形大学学術研究院産学連携教授、2022年12月より慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授。ICT CONNECT 21理事、日本CHRO協会理事、日本パブリックアフェアーズ協会理事、SDGs Innovation HUB理事、デジタル田園都市国家構想応援団理事、オープンバッジ・ネットワーク理事、ISO/TC 260国内審議委員会副委員長などを兼任。
